自己都合で退職した場合、失業手当がいつから受け取れるのか、手続きはどう進むのか気になりますよね。この記事を読めば、自己都合退職における失業手当の受給開始時期が明確に分かります。結論から言うと、失業手当はハローワークでの手続き後、原則として7日間の待機期間と、2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間が経過してから受け取れます。具体的な流れや、早くもらう方法、注意点まで詳しく解説します。
自己都合退職の場合 失業手当はいつから受け取れる?
自己都合で会社を退職した場合、失業手当(正確には雇用保険の基本手当)は、手続き後すぐにもらえるわけではありません。受給開始までには一定の期間が必要となります。ここでは、自己都合退職における失業手当の受給開始時期について、基本的なルールを詳しく解説します。
原則は待機期間と給付制限期間の後
自己都合退職の場合、失業手当を受け取るためには、「待機期間」と「給付制限期間」という2つの期間を満了する必要があります。ハローワークで求職の申込みを行い、受給資格が決定された後、まず7日間の「待機期間」が始まります。この待機期間が満了した翌日から、さらに原則として2ヶ月または3ヶ月の「給付制限期間」に入ります。実際に失業手当が銀行口座に振り込まれ始めるのは、この給付制限期間が終わった後、最初の失業認定日を経てからとなります。
つまり、自己都合退職の場合、失業手当の受給開始は、ハローワークでの手続き開始から早くても約2ヶ月と7日後、場合によっては約3ヶ月と7日後になる、と理解しておきましょう。
失業手当受給の最初の関門 待機期間とは
待機期間とは、ハローワークに離職票を提出し、求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間のことを指します。この期間は、本当に失業状態にあるかを確認するための期間とされており、自己都合退職か会社都合退職かに関わらず、すべての受給資格者に適用されます。
待機期間中は失業手当は支給されません。この7日間が経過することで、初めて失業手当の支給対象期間に入ることができます。注意点として、待機期間中にアルバイトなどで収入を得ると、その日は待機期間としてカウントされず、期間が後ろ倒しになる可能性があります。
自己都合退職特有の給付制限期間について
待機期間満了後、自己都合退職者には「給付制限期間」が設けられます。これは、会社都合などやむを得ない理由での離職者との公平性を保つため、また、安易な離職を防ぐ目的で設定されている期間です。この給付制限期間中も、待機期間と同様に失業手当は支給されません。
給付制限期間の長さは、離職理由や過去の受給歴によって異なり、原則として2ヶ月または3ヶ月となります。
給付制限期間が2ヶ月になる自己都合退職
2020年10月1日以降に離職した方については、正当な理由がない自己都合退職の場合でも、給付制限期間は原則として「2ヶ月」となります。ただし、これには条件があり、「5年間のうちに自己都合退職による給付制限を受けた回数が2回まで」の場合に限られます。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 初めて失業手当を受給する自己都合退職
- 過去に自己都合退職で失業手当を受給したことがあるが、前回の受給から5年以上経過している場合
- 過去5年以内に自己都合退職による給付制限を受けた回数が1回のみの場合(今回が2回目)
給付制限期間が3ヶ月になる自己都合退職
以下のケースに該当する場合、自己都合退職であっても給付制限期間は「3ヶ月」となります。
- 過去5年以内に、正当な理由のない自己都合退職による給付制限を既に2回受けている場合(今回が3回目以降の自己都合退職となる場合)
- 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合(懲戒解雇など。形式上は自己都合退職として処理されていても、実質的にこれに該当するとハローワークが判断した場合)
自分がどちらのケースに該当するか不明な場合は、ハローワークで確認することをおすすめします。
自己都合退職における失業手当の受給開始までの期間をまとめると、以下のようになります。
| 区分 | 待機期間 | 給付制限期間 | 受給開始までの最短期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 自己都合退職(原則: 5年で2回まで) | 7日間 | 2ヶ月 | 約2ヶ月+7日後 |
| 自己都合退職(5年で3回目以降) | 7日間 | 3ヶ月 | 約3ヶ月+7日後 |
| 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇 | 7日間 | 3ヶ月 | 約3ヶ月+7日後 |
※上記はあくまで目安であり、手続きの状況や失業認定日によって実際の振込日は異なります。
自己都合退職でも失業手当を早くもらう方法はある?
自己都合で退職した場合、原則として失業手当の受給までには7日間の待機期間に加えて、2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間があります。しかし、特定の条件を満たすことで、この給付制限期間がなくなったり、短縮されたりするケースがあります。少しでも早く失業手当を受け取り、安心して次の仕事探しに専念したい方は、ご自身が該当するかどうかを確認してみましょう。
ここでは、自己都合退職でも失業手当を早くもらうための具体的な方法について解説します。
特定理由離職者に該当すれば給付制限なしも
自己都合退職であっても、離職の理由が「正当な理由のある自己都合退職」であるとハローワークに認められた場合、「特定理由離職者」として扱われます。特定理由離職者と認定されると、会社都合退職などと同様に、給付制限期間なしで失業手当を受け取ることが可能になります。つまり、7日間の待機期間満了後、最初の失業認定日から失業手当が支給されることになります。
特定理由離職者として認められる可能性がある「正当な理由」には、主に以下のようなケースがあります。
- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷など: 医師の診断書などに基づき、就労が困難になったと判断される場合。
- 妊娠、出産、育児等による離職: 離職後、受給期間延長措置を受けていた方が、働ける状態になった場合。
- 家庭の事情の急変: 親族(父母、配偶者、子など)の死亡、疾病、負傷、または常時介護が必要になったことにより、離職を余儀なくされた場合。
- 配偶者や扶養親族との別居生活継続が困難になったことによる住所移転: 転勤がない職場に勤めていたが、配偶者の転勤等により、やむを得ず転居し通勤が不可能または困難になった場合など。
- 通勤困難: 結婚に伴う住所変更や、公共交通機関の廃止・運行時間の変更、事業所の移転などにより、通勤時間が往復でおおむね4時間以上となり、通勤が著しく困難になったと認められる場合。
- 希望退職者の募集への応募: 会社の人員整理などを目的とした希望退職制度に応募して離職した場合(ただし、会社都合退職として扱われるケースもあります)。
これらの理由に該当するかどうかは、個別の具体的な状況に基づき、ハローワークが最終的に判断します。申請の際には、離職理由を客観的に証明するための書類(診断書、住民票、辞令、介護が必要であることを示す書類など)の提出が求められます。ご自身の状況が該当する可能性がある場合は、事前にハローワークに相談し、必要な書類を確認しておきましょう。
給付制限期間が短縮される条件を確認
特定理由離職者に該当しない自己都合退職の場合でも、給付制限期間が従来の3ヶ月から2ヶ月に短縮されるケースがあります。
2020年10月1日以降の離職から、「正当な理由がない自己都合退職」の場合、過去5年間に自己都合退職した回数が2回までであれば、給付制限期間は2ヶ月となります。これは、労働者の自発的な転職を円滑にし、再就職を促進するための措置です。
ただし、過去5年間に「正当な理由がない自己都合退職」を3回以上繰り返している場合は、原則通り3ヶ月の給付制限期間が適用されます。この回数は、ハローワークで受給資格を決定する際に確認されます。
給付制限期間のパターンをまとめると、以下のようになります。
| 離職理由の区分 | 過去5年間の自己都合退職回数(正当な理由なし) | 給付制限期間 |
|---|---|---|
| 特定理由離職者 | 問わない | なし |
| 自己都合(正当な理由なし) | 1回目または2回目 | 2ヶ月 |
| 自己都合(正当な理由なし) | 3回目以降 | 3ヶ月 |
| 会社都合・特定受給資格者 | 問わない | なし |
ご自身の離職がどのケースに該当し、給付制限期間がどれくらいになるか正確に知りたい場合は、離職票を持参の上、ハローワークの窓口で確認するのが最も確実です。いずれの場合も、失業手当を受給するためには、7日間の待機期間を満了し、定められた求職活動を行う必要があります。
失業手当はいつまで受け取れる?受給期間について
失業手当が「いつから」もらえるかと同様に、「いつまで」もらえるのかも重要なポイントです。ここでは、自己都合退職の場合の失業手当を受け取れる期間について詳しく解説します。
自己都合退職の所定給付日数
失業手当を受け取れる最大の日数を「所定給付日数」といいます。この日数は、離職理由や年齢、そして雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)によって異なります。
自己都合で退職した場合の所定給付日数は、雇用保険の被保険者であった期間に応じて、以下の表のように定められています。会社都合退職や特定理由離職者と比較すると、日数は短くなる傾向にあります。
| 雇用保険の被保険者であった期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
(注)自己都合退職の場合、年齢による所定給付日数の違いはありません。
例えば、雇用保険に8年間加入していた方が自己都合で退職した場合、所定給付日数は90日となります。この90日分を上限として、失業認定を受けた日数分の失業手当が支給されることになります。
失業手当の受給期間の原則と延長措置
失業手当を受け取ることができる期間を「受給期間」といいます。これは、原則として離職日の翌日から1年間です。この1年間の受給期間内に、上記の「所定給付日数」分を限度として失業手当を受け取る必要があります。
例えば、所定給付日数が90日の方の場合、離職日の翌日から1年以内に、失業認定を受けた日が合計90日に達するまで手当が支給される、ということです。
注意すべき点は、受給期間(原則1年)を過ぎてしまうと、たとえ所定給付日数が残っていても、その残りの日数分の失業手当は受け取れなくなるということです。そのため、退職後は早めにハローワークで手続きを開始することが重要です。
ただし、この受給期間(原則1年)の間に、病気、けが、妊娠、出産、育児(3歳未満の子に限る)、親族等の介護といった理由で、引き続き30日以上働くことができなくなった場合は、ハローワークに申請することで受給期間を延長できる制度があります。
延長できる期間は、働けなくなった日数(最大で3年間)です。これにより、本来の受給期間1年と合わせて最長で4年間まで、失業手当を受け取れる可能性のある期間を延ばすことができます。
受給期間の延長申請は、働けなくなった状態が30日続いた日の翌日から起算して、原則1か月以内に、ご自身の住所または居所を管轄するハローワークに申請書を提出する必要があります。代理人による提出や郵送も可能です。
申請には「受給期間延長申請書」のほか、離職票(持っている場合)や、延長理由を証明する書類(医師の診断書、母子健康手帳など)が必要となります。必要書類については、事前にハローワークに確認しておくとスムーズです。
受給期間を延長している間は、働くことができない状態であるため、失業手当は支給されません。その後、働ける状態になった際に、改めてハローワークで求職の申込みと受給手続きを行うことで、残りの所定給付日数分の失業手当を受け取ることが可能になります。
自己都合退職で失業手当をもらう際の注意点
自己都合で退職した場合、失業手当(基本手当)を受け取るまでには待機期間や給付制限期間があり、会社都合退職の場合よりも受給開始が遅くなります。スムーズに、そして確実に失業手当を受給するためには、いくつか注意すべき点があります。ここでは、特に重要な3つのポイントを解説します。
給付制限期間中も求職活動の実績が必要
自己都合退職の場合、7日間の待機期間の後、原則として2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間が設けられます。この期間中は失業手当が支給されませんが、給付制限期間が明けた後に失業手当を受け取るためには、この期間中も求職活動を行っている実績が必要となります。
給付制限期間が明けた最初の失業認定日には、給付制限期間中の求職活動の実績を「失業認定申告書」に記載して提出する必要があります。具体的には、以下のような活動が求職活動として認められます。
- 求人への応募(書類選考、面接など)
- ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講
- 許可・届出のある民間職業紹介機関、労働者派遣機関が行う職業相談、職業紹介、求職活動方法を指導するセミナー等の受講
- 公的機関(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体など)が実施する職業相談、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講・参加
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
失業認定を受けるためには、原則として認定対象期間中に2回以上(給付制限期間中は合計で3回以上など、地域や状況により異なる場合があります)の求職活動実績が必要です。必要な活動回数や認められる活動の詳細は、必ず管轄のハローワークに確認しましょう。求職活動の実績が不足していると、失業手当の支給が先送りされたり、不支給となったりする可能性がありますので、計画的に活動を進めることが重要です。
失業手当受給中のアルバイト収入に注意
失業手当は、失業中の生活を支え、一日も早く再就職するための給付金です。そのため、受給期間中にアルバイトやパートタイマーとして働くこと自体は可能ですが、収入額や労働時間によっては失業手当が減額されたり、支給されなくなったりする場合があるため、注意が必要です。
アルバイト等で収入を得た場合は、必ず4週間に1度の失業認定日に提出する「失業認定申告書」で正直に申告しなければなりません。もし申告しなかったり、虚偽の申告をしたりすると、不正受給とみなされ、受け取った手当の全額返還はもちろん、その2倍に相当する金額(合計3倍)の納付を命じられる可能性があります。絶対にやめましょう。
失業手当の支給調整に関するルールは少し複雑ですが、基本的な考え方は以下の通りです。
| ケース | 失業手当への影響(概要) | 注意点 |
|---|---|---|
| 待機期間中のアルバイト・パート | 原則として認められません。収入の有無にかかわらず、働いた場合は待機期間が延長される可能性があります。 | 短時間であっても、必ず事前にハローワークに相談・確認してください。 |
| 受給期間中の1日の労働時間が4時間未満のアルバイト・パート | 収入額に応じて、その日の失業手当が減額または不支給となる場合があります。控除額を超えた収入があると減額対象となります。 | 収入があった日、収入額を正確に失業認定申告書に記載する必要があります。 |
| 受給期間中の1日の労働時間が4時間以上のアルバイト・パート | その日は「就職」または「就労」したとみなされ、失業手当は支給されません。ただし、支給されなかった日数分は受給期間満了日まで繰り越されます(支給が後ろにずれる)。 | 働いた日を正確に失業認定申告書に記載する必要があります。週20時間以上の労働が見込まれる場合は雇用保険の加入対象となり、「就職」したと判断される可能性が高まります。 |
上記の基準はあくまで目安です。内職や手伝いなども収入や労働時間として申告が必要な場合があります。判断に迷う場合は、必ず事前に管轄のハローワークに相談し、指示に従うようにしてください。
失業手当の申請には期限がある
失業手当を受け取ることができる期間(受給期間)は、原則として離職した日の翌日から1年間です。この1年間のうちに、定められた所定給付日数分の失業手当を受け取る必要があります。
自己都合退職の場合、給付制限期間(2ヶ月または3ヶ月)があるため、実際に手当を受け取れる期間はさらに短くなります。例えば、所定給付日数が90日の人が、離職から3ヶ月後に初めて申請した場合、受給期間満了までに90日分の手当を受け取れない可能性があります。
したがって、失業手当の申請手続きは、離職後できるだけ速やかに行うことが重要です。退職したら、まずは必要書類(特に離職票)を準備し、住所地を管轄するハローワークで求職の申込みと受給資格の決定手続きを行いましょう。手続きが遅れれば遅れるほど、受け取れるはずの手当を満額受け取れなくなるリスクが高まります。
なお、病気、けが、妊娠、出産、育児(3歳未満)、親族の介護など、やむを得ない理由で引き続き30日以上働くことができなくなった場合は、受給期間の延長(最大3年間)を申請できる場合があります。ただし、延長できるのはあくまで「受給期間」であり、「所定給付日数」が増えるわけではありません。延長申請にも期限がありますので、該当する場合は早めにハローワークに相談してください。
まとめ
自己都合退職の場合、失業手当はすぐには受け取れません。ハローワークで求職申込みを行った後、7日間の待機期間が満了し、さらに原則として2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間が経過してから支給が開始されます。給付制限期間は、過去5年間の自己都合退職の回数などによって決まります。失業手当を受給するには、待機期間や給付制限期間中も含め、定められた求職活動実績が必要です。手続きの流れや注意点をしっかり理解し、計画的に行動することが大切です。
退職給付金の受給手続きを行うためには、正確な手続きと専門的な知識が必要です。
しかし、手続きの複雑さや専門知識の不足でお困りの方も多いのではないでしょうか?「退職のミカタ」なら、業界最安レベルの価格で安心してご利用いただけます。「退職のミカタ」のコンテンツを利用することで、退職前から退職後まで、いつ・どこで・何をすればいいのかを、確認しながら進めていくことができます。退職給付金についてお困りの方は、ぜひ「退職のミカタ」のご利用をご検討ください!

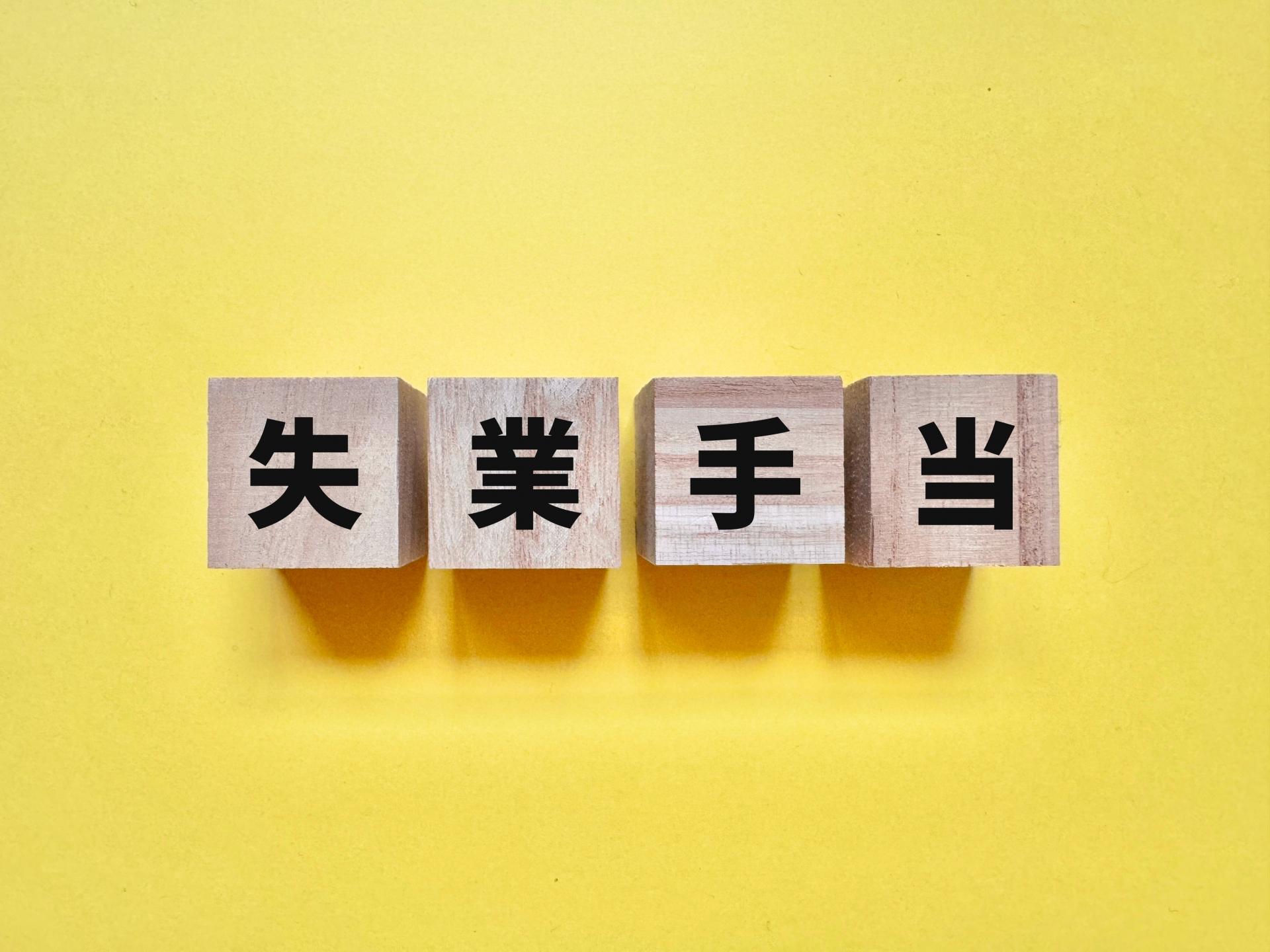





コメント